第9回 埼玉臨床眼科セミナーのご案内
謹啓
時下、先生におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
埼玉県下で眼科診療に携わる病院と診療所との医療連携を深め、より充実した眼科医療の提供を目的とした「埼玉臨床眼科セミナー」も第9回を迎えることができました。これまでご参加いただき先生方に心より御礼申し上げます。今回は、防衛医科大学校の佐藤智人先生による教育講演の他、特別講演では、江口眼科病院院長の江口秀一郎先生には乱視矯正トーリックレンズの適切な症例選択と使用法について、そして産業医科大学眼科教授の近藤寛之先生には小児の網膜剥離疾患に対する新たな考え方についてお話戴きます。講演会後は情報交換会をご用意しておりますので、学術、医療を通してより親交を深めて戴ければ幸甚です。多くの先生方のご参加を心よりお待ち申し上げております。
防衛医科大学校 眼科学教室
教授 竹内 大
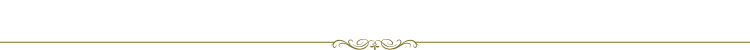
白内障術後乱視は網膜イメージのボケの原因となるため白内障術後裸眼視力を低下させる。乱視コントロールと矯正を目的として、様々な方法が試みられてきた。眼内レンズに円柱度数を加えて乱視矯正する試みは10年以上前に我が国で発案されたが、当時の眼内レンズ素材はPMMAであったため、大きな手術切開創が必要であり、手術惹起乱視が大きく、術後乱視度数が不安定であったことや、眼内レンズ乱視軸の術後変動が問題となり、広く一般臨床に普及することは無かった。2009年に新たなアクリル製トーリック眼内レンズが臨床使用可能になって以来、その術後成績が良好であることと相まって、白内障手術時における乱視矯正への関心が高まっている。しかし、調節機能がほぼ失われたIOL挿入眼においては、術後角膜乱視をゼロにすることが本当に理想的な術後屈折状態なのであろうか?軽度の白内障術後乱視は焦点深度を広げ、白内障手術後裸眼視機能の質を向上させる。更に、乱視が視力をはじめとする視機能に及ぼす影響の検討は、片眼視における乱視度数や乱視軸の変化を検討した報告が大半である。しかし、実際の白内障術後患者の大半は両眼開放下で日常生活を送っており、片眼視における乱視の視機能に及ぼす影響の評価は乱視が視機能に及ぼす影響を過大評価している可能性がある。今回の講演では、両眼開放下の視機能測定において、片眼乱視や両眼乱視の及ぼす影響を直乱視、倒乱視、斜乱視に分けて検討し、どの様な乱視がどの程度視機能に影響を及ぼすかを検討し且つ両眼視をしている状態でどの様な乱視を積極的に矯正すべきかを理論的に考えてみたい。併せてトーリック眼内レンズの長期成績を供覧し、もって、この新たな眼内レンズの適切な症例選択と使用法を再考してみたい。
小児の網膜剥離は日常の診療では遭遇する機会が少ないだけでなく、牽引性や滲出性剥離など特殊な病態を呈するものもありその病像を理解するのは少し大変です。これらの疾患は診断の遅れにより重症化しやすいものの、成人と比べ治療により視力が回復する傾向があり、できるだけ早期にかつ適切に診断する必要があります。また、小児の網膜剥離は何らかの基礎疾患を有しており、治療の成否はこれら基礎疾患の病態と大きく関係するので、その原因を究明することも重要です。今回は未熟児網膜症や家族性滲出性硝子体網膜症、Stickler症候群などの疾患をとりあげ、診断法の進歩や治療法についての最近の知見をとりあげながら、小児の網膜剥離疾患に対する考え方がどのように変わってきたかを紹介したいと思います。
共催:埼玉臨床眼科セミナー/千寿製薬株式会社